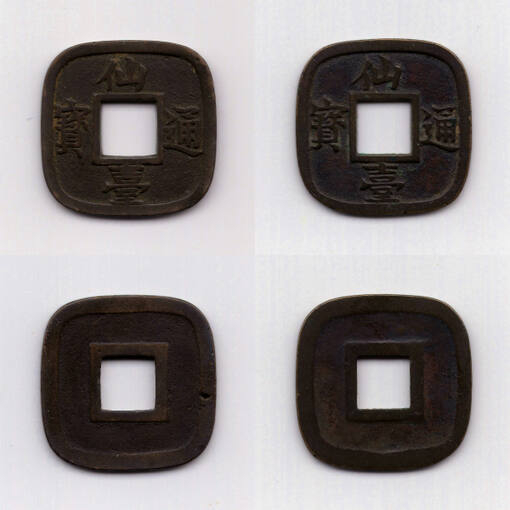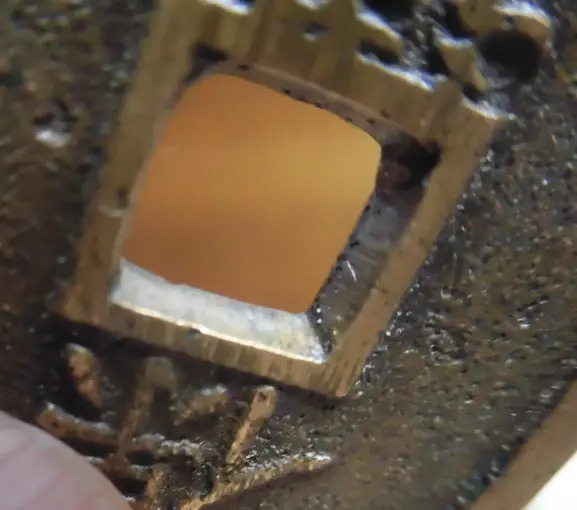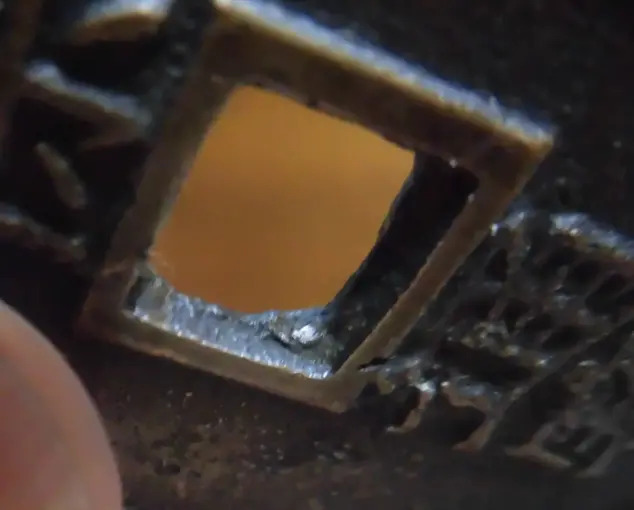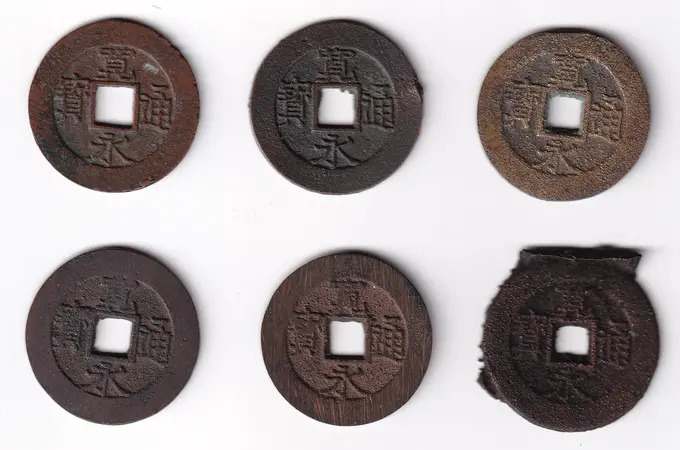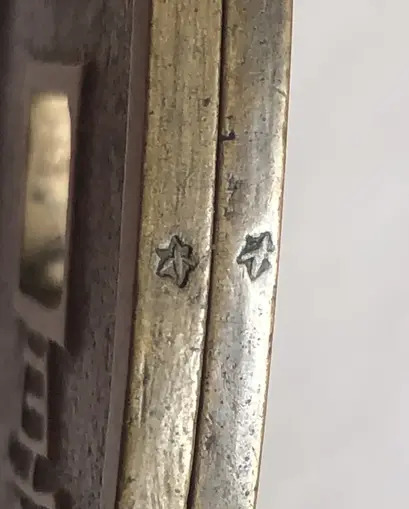浩泉丸 投稿日: 2024年04月17日 09:38:32 No.1118 【Home】
とら 投稿日: 2024年04月17日 09:40:25 No.1119
とら 投稿日: 2024年04月17日 09:45:28 No.1120
|
|
とら 投稿日: 2024年04月12日 23:52:41 No.1112
|
|
浩泉丸 投稿日: 2024年04月05日 08:40:55 No.1104 【Home】
|
旭泉亭 投稿日: 2024年03月31日 11:00:22 No.1096
|
とら 投稿日: 2024年03月30日 09:39:51 No.1089
|
とら 投稿日: 2024年03月25日 13:56:32 No.1084
|
笑門泉 投稿日: 2024年03月23日 06:10:00 No.1080
関西のT 投稿日: 2024年03月23日 11:48:17 No.1082
|
関西のT 投稿日: 2024年03月09日 19:37:21 No.1056
とら 投稿日: 2024年03月10日 13:43:18 No.1059
とら 投稿日: 2024年03月12日 12:02:13 No.1063
関西のT 投稿日: 2024年03月16日 13:51:51 No.1071
関西のT 投稿日: 2024年03月16日 14:20:13 No.1072
とら 投稿日: 2024年03月16日 17:48:20 No.1074
とら 投稿日: 2024年03月17日 17:12:18 No.1075
|
とら 投稿日: 2024年03月10日 22:19:14 No.1061
|
|
|
Powered by Rara掲示板