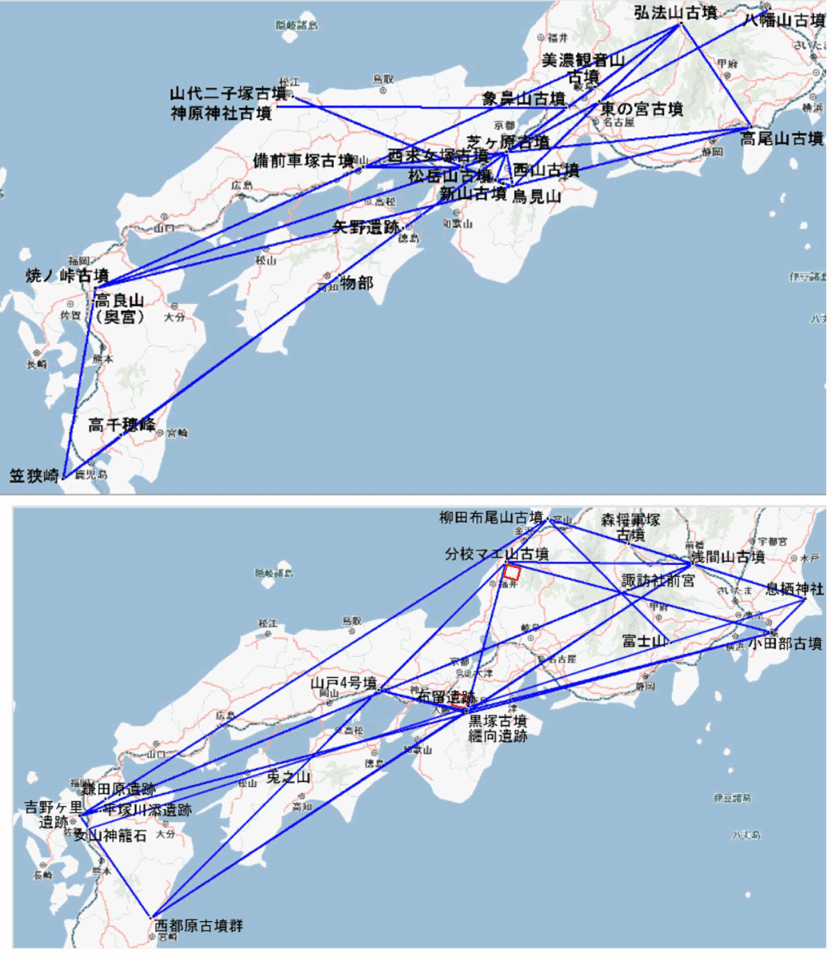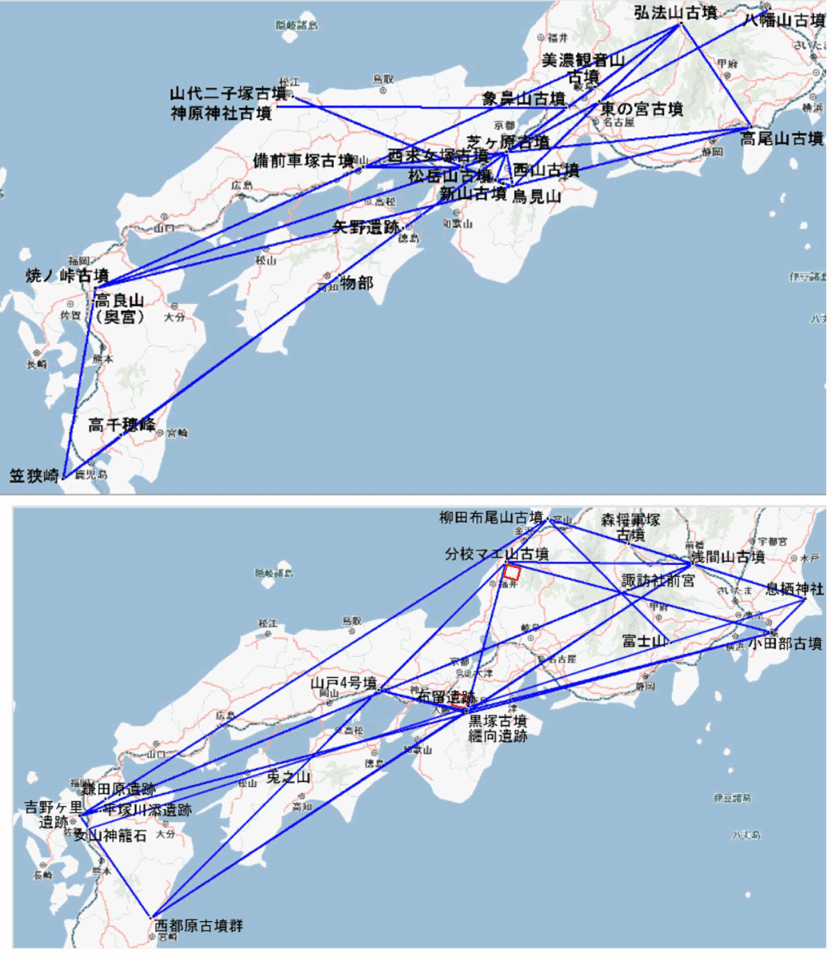投稿者:管理人
以前、畿内の邪馬台国時代に関連する古墳や遺跡、当時卑弥呼に銅鏡を賜与した魏の紀年銘を記した銅鏡の出土地を結んだ方位ラインを作成したことがありますが、今回、邪馬台国畿内説で卑弥呼の都とみなされている奈良の纒向遺跡と同様な構造を持つ滋賀県の伊勢遺跡を知る機会があり、この遺跡に関連するラインを洗いなおしてみました。
その作成したラインが図1となります。
ここでは、まず、安満宮山古墳(魏紀年銘鏡出土)⇔伊勢遺跡(滋賀)⇔象鼻山1号墳(3世紀末前方後方墳)への東30度偏角のラインがあり、このラインと太田南古墳群⇔安満宮山古墳⇔黒塚古墳(三角縁神獣鏡大量出土)への西60度偏角のラインが直交しています。
同じく黒塚古墳⇔伊勢遺跡⇔分校マエ山古墳への東75度偏角のラインがあります。
その分校マエ山古墳を起点とするものとしては、分校マエ山古墳⇔太田南古墳群(魏紀年銘鏡出土)南部⇔森尾古墳(魏紀年銘鏡出土)への東30度偏角のラインがありますが、このラインと先の安満宮山古墳⇔伊勢遺跡への東30度偏角のライン、同じく先の太田南古墳群⇔安満宮山古墳への西60度偏角のラインとが直交しています。
また分校マエ山古墳⇔伊勢遺跡⇔豊日神社(布留遺跡西部)⇔黒塚古墳への東75度偏角のラインがあります。
その他、森尾古墳⇔安満宮山古墳への西45度偏角のライン、同じく森尾古墳⇔広峯15号墳(魏紀年銘鏡出土)⇔豊日神社への西50度偏角のラインもあります。
そして、図のように、太田南古墳群⇔黒塚古墳⇔象鼻山1号墳を結ぶ三角形の垂線上に伊勢遺跡周辺地域が位置していることがあり、この場所が当時の畿内周辺を統治するのに相応しい場所であったことも伺えます。
その伊勢遺跡周辺地域については、伊勢遺跡群があり、伊勢集落が政治と祭祀を、下鈎集落が工業を、下長集落が商業を分担する「機能別都市構成」がなされていたと考えられています。詳細はこちらのサイトをご参照ください。遺跡群の地図も図2として引用します。
「伊勢遺跡-守山弥生遺跡研究会」伊勢遺跡群
https://ise-iseki.yayoiken.jp/isekigun.htm
この図2の中で、伊勢遺跡北西にある山田遺跡がありますが、邪馬台国関連遺跡には山田の字名がつくことが多いことがあり、この地も邪馬台国の主要な拠点であった可能性が高いでしょう。
実際、前述した伊勢遺跡周辺を通過する各種ラインのうち、安満宮山古墳⇔象鼻山1号墳へのラインは山田遺跡を通過することもわかります。
年代的にも邪馬台国時代にあたる、弥生時代後期後半がこの遺跡の発展時期とのことで、九州から邪馬台国の勢力が東遷によって畿内へと拡大していく過程で、この地が主要な拠点となっていったのではないでしょうか。
その時期は女王卑弥呼もしくはその次の女王・台与の時代に関わる可能性がありそうですが、その東遷の主体には、ニギハヤヒを祖とする物部氏の影響を考慮すべきで、実際、伊勢遺跡から山田遺跡の間に物部(村)の字名がみえることにも留意しておくべきでしょう。
以前、卑弥呼とその姪であろう台与について、物部氏系で孝元・開化天皇妃となったウツシコメとその姪のイカガシコメに対応していることを指摘したことがありますが、この時期に物部氏の影響力が強かったことを考慮しても、邪馬台国の都周辺に物部氏の影響をうけた拠点があるはずです。
そのことは、前述した黒塚古墳⇔象鼻山1号墳へのラインが、物部氏の拠点の石上神宮や布留遺跡(布留式土器出土)東部の豊日神社周辺を通過することがあり、この周辺にある豊井・豊田の地名も、女王・台与(トヨ)と関わっていた可能性を考えてきたこともあります。
そのラインの延長線上には、纒向遺跡があり、そこに隣接するヤマトトヒモモソヒメ陵の箸墓古墳周辺にも豊田の字名が残ることがあります。
この豊日神社については、前掲した豊日神社⇔広峯15号墳⇔森尾古墳へのラインがあり、その森尾古墳からは、卑弥呼に鏡を与えた魏の正始元年(西暦240年)の銘文があり、同じく広峯15号墳からも、同じの景初四年(非実在の年号・西暦240年)の銘文が記されていることがあります。
ところで、前掲の三角形を形成するライン上にある安満宮山古墳と太田南5号墳からは、青龍三年(235年)方格規矩四神鏡が出土していることがあり、年代的に5年ですが上記の森尾古墳に関わるラインより古いことがわかります。
実際、今回のライン図をみても、双方のラインには、ずれがあり、構築年代に相違があったことも伺えますが、前者については、邪馬台国時代の指標とされる庄内式どきより新しい布留式土器を出土した布留遺跡周辺を通過することがあり、これを仮に女王台与が支配した250年代から60年代の構築と考えると、後者のラインについては、それ以前の235年頃の卑弥呼の時代には構築されていた可能性が出てくるでしょう。
伊勢遺跡については、後代の伊勢神宮との関わりも予想できますが、崇神天皇の年代を253年以降として、その時期に伊勢神宮が創始されたことを考えると、其れ以前に宮中で祀られていたアマテラス女神の存在を考慮しておくべきでしょう。
一説にはアマテラス女神と卑弥呼を同一視する見方もありますが、卑弥呼が果たして、この伊勢遺跡周辺にいたのが、それとも東遷前の九州や四国方面にいたのかについて確証するために必要となってくるのが、卑弥呼の径百歩の墓の存在となりそうです。
卑弥呼の墓が仮に畿内にあるとして、今回のライン上に位置するならば、伊勢遺跡周辺、もしくは、太田南古墳群、安満宮山古墳、黒塚古墳、象鼻山1号墳あたりが候補地に上がってくるはずです。
その象鼻山1号墳については、象鼻山の最高所に位置する前方後方墳で、全長約42.80m、後方部長22.95m、後方部幅25.86m、後方部高さ4.23m、前方部長17.15m、前方部幅14.40m、前方部高さ2.96m、濃尾平野に面する後方部東側のみ二段築成とし、部分的に葺石を備えています。埋葬施設からは鏡や石製品、刀、剣などが発見され、その築造時期は3世紀中頃と考えられています。
同じく安満宮山古墳の墳形は長方形で、規模は東西18メートル、南北21メートルと推定される、葬施設はコウヤマキ製の割竹形木棺の直葬。3世紀後半の築造と推定されています。
同じく太田南古墳群のうち、上記の魏年号銘鏡を出土した5号墳は、12m×19mの方墳で組合せ式石棺、4世紀後半の築造とされます。
同じく黒塚古墳は、全長約130メートルの前方後円墳で、後円部径約72メートル、高さ約11メートル、前方部長さ約48メートル、高さや6メートル、三角縁神獣鏡33面とそれよりも少し古い画文帯神獣鏡1面が出土し、北東隅に大小2本の鉄棒をU字形に曲げた用途不明の鉄製品が立てかけられていた。大小2本の棒の間にはV字形の鉄製の管が、複数、付着または崩落し、この管で鋸歯状に大小のU字形鉄棒を結び付けていた形跡がある。
ここで、黒塚古墳以外は、方墳、もしくは前方後方墳と、後に主流となる前方後円墳ではない点に留意しておくべきでしょう。そして、20-25m前後の尺度で構築されている点でも共通性があります。
そこで、その他の魏の紀年銘鏡を出土した古墳を調べていくと、下記のようになります。
まず、魏の景初三年(239年)銘の三角縁神獣鏡を出土した神原神社古墳についても、方墳で、復元した場合の規模は29m×25m、高さは5m程とされます。島根県で最古期の前期古墳とされます。
次に柴崎蟹沢古墳は古墳時代前期(4世紀)ころに築造された径12メートルの円墳(長22メートルの方墳との説も)であり、正始元年(240年)銘の三角縁神獣鏡が出土しています。
次に森尾古墳ですが、35×24m前後の南北に長い基底部をもつ、方形台状の墳丘が想定されています。正始元年(240年)銘の三角縁神獣鏡が出土しています。
次に、広峯15号墳は、直径40m、後円部径25m、前方部径13mの前方後円墳で、4世紀後半の築造、「景初四年(240年)」の銘の盤龍鏡が出土しています。
次に竹島古墳は全長56メートル、後円部径35メートルの前方後円墳で、4世紀前半の築造、正始元年(240年)銘の三角縁神獣鏡が出土しています。
次に持田48号墳は、全長78m、後円部径50m・高さ7.3m、前方部幅27m・高さ4m の柄鏡式前方後円墳で、、景初四年(240年)銘入り斜縁盤龍鏡が、この古墳から出土された(伝)があります。
このように、特に神原神社古墳、森尾古墳が方墳であり、柴崎蟹沢古墳も方墳だとすると、22~25m前後の方形部をもつ古墳である点で、先の古墳と同様な特徴と持つと言えるでしょう。広峯15号墳も円墳ですが、25mがみえます。
このような、22~25m前後の方墳として思い出されるのが、九州高良山そばの祇園山古墳で、形状は方墳で、規模は東西約23.7メートル、南北約22.9メートル、高さ約6メートル、主体部(石棺)、築造時期が3世紀中期であると考えられているケースがあります。規模とも吉野ケ里遺跡の楕円状構築物の上に築造された方形墳丘墓および楽浪漢墓(阿残墓)石巌里第9号墳に類似するとされ、墳丘外周からは、66人分以上と推定される甕棺墓3基、石蓋土壙墓32基(未調査5・不明2を含む)、箱式石棺墓7基、竪穴式石室墓13基、構造不明7基の埋葬施設が確認されていることなどから、卑弥呼の墓として有力視されていることもあります。
あと、今回のライン分析では北陸の分校マエ山古墳があり、1号墳が全長37mの纏向型前方後円墳とされており、それより古いとされる6号墳(前方後円墳)との間に方墳が複数挟まれていることもあります。
ライン的には、この古墳は、黒塚古墳と、森尾古墳とに接続しており、以前作成した図3の上図のように、初期の前方後円墳、特に纏向型前方後円墳とに接続関係があると言えます。
また象鼻山1号墳については、前方後方墳となりますが、以前作成した図3の下図のように、全国各地の前方後方墳、特に長野の弘法山を起点とした。弘法山古墳⇔象鼻山1号墳⇔芝ヶ原古墳⇔矢野遺跡⇔物部(高知市)⇔高千穂峰南部⇔笠狭崎への東35度ライン上に位置していることが重要です。
この前方後方墳に関する拠点は物部氏との関わりが想定されており、図のように、象鼻山1号墳⇔神原神社古墳への東西同緯度ラインの存在も確認できます。
その出雲方面の神原神社古墳も方墳とのことがあり、前方後方墳と方墳との間には相関性があることも予想できるでしょう。
また、その辺の方墳・前方後方墳、そして纏向型前方後円墳との関係についても、今年もこれから考察をすすめていきたいと思います。